台風15号 各地で被害、静岡市清水区では大規模断水「想定外のリスク」にどう対応するか【重大ニュース静岡2022】
「こちらの住宅街、冠水しています。そしてここに住む住民でしょうか。膝よりも高い位置まで水に浸かってしまっています」
- YouTube
各地に深い爪痕

桜井健至記者:
「あちらに見える穴にトラックが落ちていたということです」
髙橋諒記者:
「あちらが台風の影響で土砂崩れが起きた現場です。山肌が露わになっています」
9月、記録的な大雨によって県内に深い爪痕を残した台風15号。
伊地健治アナウンサー:
「清水区小島町の承元寺取水口です。たくさんの流木やがれきなどが詰まってしまっているのがわかります。ヘルメットを被った作業員の方でしょうか。溜まった流木、がれきを撤去している様子が見えます」
「復旧にどれだけ時間がかかるか想像ができなかった」
特に大きな被害が出たのが静岡市清水区です。
須藤誠人アナウンサー:(19日)
「台風15号の発災からおよそ3カ月が経ちました。今では興津川は穏やかに流れていますが、取水口の方を見てみると鉄製の柵がひしゃげていたり、護岸が崩れていたりと台風15号による被害の大きさを物語っています」

興津川にある「承元寺取水口」。
ちょうど3カ月前、ここに真っ先に駆け付けたのが…。
静岡市上下水道局 清水水道施設担当 川越勝浩課長:
「舗装が新しくなっているところが管理用道路だが、あそこにも水が流れている状態だったので、とても取水口の近くまで近寄ることができなかった。もう本当に初めての状況で唖然という言い方が正しいかどうか分からないが、非常に驚いた」
施設の管理を担当する、静岡市の川越勝浩課長です。
Q.そうした光景を目の当たりにしてどんなことを感じた?
静岡市上下水道局 清水水道施設担当 川越勝浩課長:
「復旧にどれだけ時間がかかるか想像ができなかったので、ひょっとすると広域な断水が起こるのではないかと覚悟した」
その予感は現実となります。清水区では最大6万3000軒が断水しました。
対応について批判の声も
清水区民:
妻「大変もう。すぐこれ(蛇口)こうやってやっちゃうんだよ。本当に不便」
夫「一日も早くと言うしかない。もう我慢ですね」
流木や土砂が撤去されたのは、被害判明の4日後。
自衛隊への災害派遣要請をめぐり、市民からは批判の声も上がりました。
現在はかつてと変わらない量を取水していますが、全てが元通りというわけではありません。
静岡市上下水道局 清水水道施設担当 川越勝浩課長:
「こちらが制水弁といって、取水量を調整するバルブ。今までは、遠方で開け閉めができていたものができなくなってしまったので、1日3回の点検の中で職員が連絡を取りながら開閉を調整している」
Q.これ根元から折れ曲がっているような…
「ゲートの開閉機だが、流木等の関係で押し倒されてしまった」
清水谷津浄水場
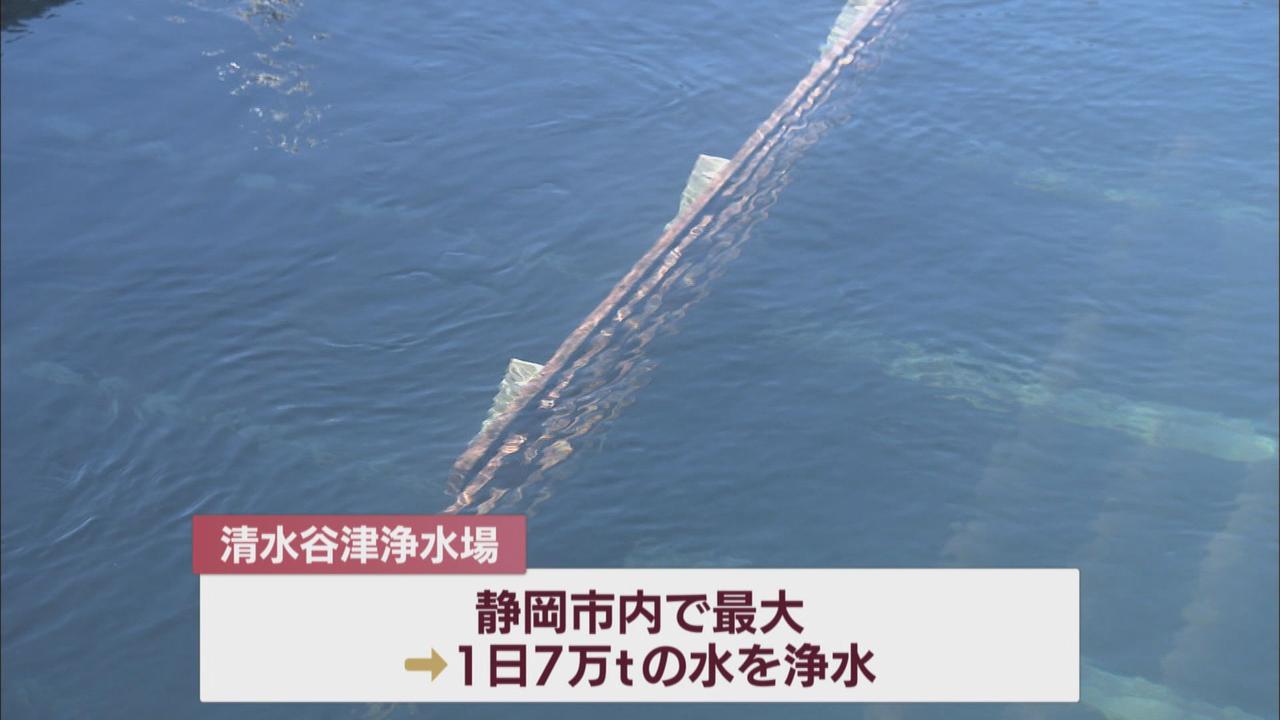
取水口から送られた水を処理して飲み水にしている、「清水谷津浄水場」。
静岡市で最も大きく、1日の浄水量は7万トンにのぼります。
清水区にある水道施設を集中して管理しているのが場内にある監視室。
表示されている数字は1時間に取り入れている水の量です。
静岡市上下水道局 清水水道施設担当 川越勝浩課長:
「承元寺取水口で水が取れなくなった関係で、取水量というところがほぼゼロになった」
Q.そういった状況は今までに見たことは?
「今まででない非常に恐ろしさを感じた」
「想定外のリスク」にどう対応するか
台風15号が引き起こした大規模な断水被害。
浮き彫りとなったのは、「一つの水源に依存するリスク」です。
“渇水”に悩まされてきた歴史のある清水区。
別の水源を活用し、対策に取り組んできましたが、災害による“断水”は想定外でした。
静岡市上下水道局 水道技術担当 星野浩之部長:
「今回の取水口全域が、水が取れなくなってしまったというレベルでは断水を回避できなかったので、新たな水源=バックアップ水源の確保について検討していきたい」
厚生労働省が東日本大震災の後に作成したガイドラインにも、複数の水源を確保する重要性が訴えられています。
静岡市は今年度中に有識者会議を設置し、 新たな水源の確保に向けて議論していくとしています。

静岡市上下水道局 水道技術担当 星野浩之部長:
「取水口そのものを強化する。土砂や流木が詰まりにくくする。そういった対策を緊急で設計を行って、来年度には実施していきたい」
想定外のリスクが現実となった今年。
年々猛威を増す自然災害が、身近に潜む課題を浮き彫りにしています。
